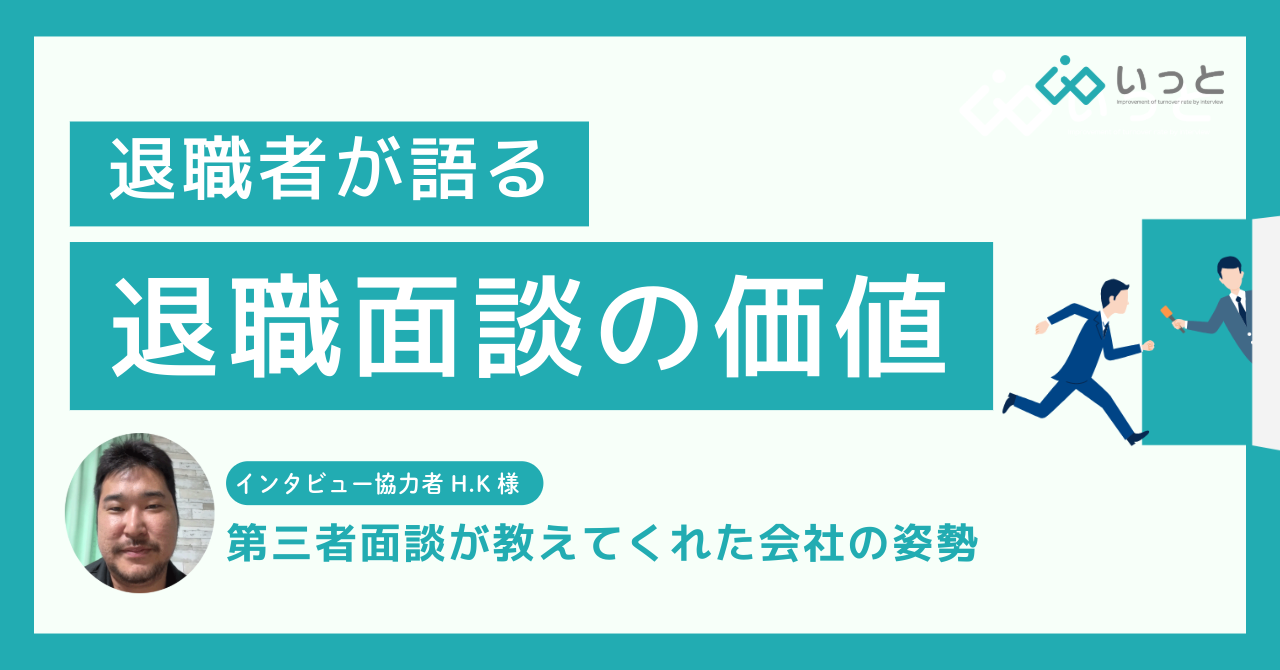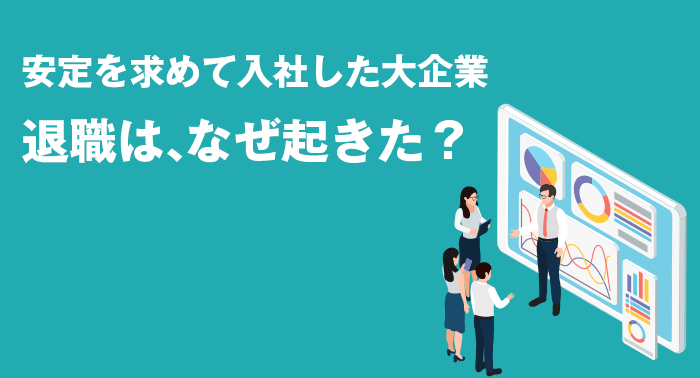離職
子どもの体調不良で休めない!家庭と仕事の両立が許されない職場文化

「在宅勤務制度はある。でも、実際には使えないんです。」
そう語ったのは、小学生の子どもを持つ営業マネージャーの里美さん(仮名)でした。
近年、多くの企業が多様な働き方に対応するために制度を整えています。しかし、制度があることと、それが社員にとって安心して使えるものであることは別の話です。
今回のインタビューでは、制度が文化として根づいていない職場が引き起こした退職の実態に迫ります。
※本記事は取材に基づいて構成されていますが、個人が特定されないようプライバシーに配慮しています。
目次
小学校の入学案内で聞かされた“働けない現実”

――退職を考えるようになったのは、どんなきっかけからだったのでしょうか?
里美さん「子どもの小学校の入学説明会でした。そこで、保護者は毎朝8時10分から20分の間に校門まで送りに来てくださいという案内を受けたんです。私は集団登校があるのかなと思っていたので、完全に想定外でした。その時間帯って、私が通勤で家を出る時間なんですよ。7時30分には出発して9時にはオフィスにいないといけない。これはもう物理的に無理だと強く感じました。」
――会社には在宅勤務制度がなかったのでしょうか?
里美さん「実は転職してきたんですが、育児との両立を意識して入社を決めたんです。
面接で在宅勤務制度はあるから直属の上司の許可をとって使ってくださいと聞いていたんです。だから、それなら育児と仕事のバランスがとれると信じて入社を決めたんですよ。」
――それなのに、実際は使えなかった?
里美さん「はい。在宅勤務制度はあるけれど、使える雰囲気がないというのが正直なところです。子どもが急に熱を出したときは在宅勤務が認められましたが、それも“特別扱い”として扱われていました。
今回、小学校の登下校の都合で「必要に応じて出勤するが、基本的に在宅勤務をしたい」と相談したところ、「それは特別扱いになるので難しい」と返されてしまったんです。ただ、仕事と家庭を両立する方法を模索しただけなのに、あまりにも冷たい対応でした。」
――職場の中で、育児への理解がある方は少なかったんですか?
里美さん「同じ部署内で子育てをしている人は、私を含めてたったの2人。そのうちの1人の女性に話を聞いたところ、彼女は時短勤務をしていました。でも、給料が下がるから本当は在宅にしたかったとも言っていたし、業務量は減らず、サービス残業で帳尻を合わせている状況でした。
私は経済的な事情もあるので、給与を下げてまで時短に切り替えるのは難しかったんです。フルタイムで働き続けられるように、在宅勤務制度がある会社で働き始めたつもりが、叶いませんでした。」
――面接時には在宅勤務について説明を受けなかったんですか?
里美さん「いえ。在宅勤務について説明は受けました。在宅勤務制度はあるため、上司に相談して働き方を決めてくださいと言われましたね。なので、説明自体は間違っているわけではないと思います。でも、部署により在宅勤務が使えるか使えないかが大きく変わりましたね。」
制度はあった。でも文化がなかった
――在宅勤務制度を使うと、どんな雰囲気になったのでしょうか?
里美さん「そうですね。在宅勤務制度を申請すると、本当に使うの?っていう空気があります。制度はあるけれど、使ってもいい雰囲気がなかったんです。」
――それは、どういった場面で感じられたのでしょうか?
里美さん「例えば、子どもが体調不良になり学校から呼び出しがあったときに、午後は在宅勤務させてくださいと伝えたら“急ぎの仕事がないなら休んだら?”って言われたことがありました。親切にも聞こえるかもしれませんが、“在宅=休みと変わらない”という前提で言われていました。実際に在宅勤務したにも関わらず、午後休扱いをされましたね。」
――制度の存在と運用が乖離していたのですね。
里美さん「一番つらかったのは、在宅勤務すること自体が特別扱いになること。私は会社の制度を利用して柔軟に働きたかっただけなのに、それを理解してもらえなかったことは悲しかったですね。」
在宅勤務の利用だけで「特別扱い」と責められた

――会社に相談する機会はありましたか?
里美さん「はい。会社の規定に沿って週2~3日の在宅勤務と子どもの登校時間に合わせた時差出社の組み合わせて申請しました。その際にも“特別扱いはできません”とはっきり言われました。」
――会社の規定に沿っていたにも関わらず?
里美さん「はい。同じような働き方をしている人がいないから難しいと。また特別なルールを認めると他の社員との公平性に欠けると言われましたね。私は、他の人より楽をしようとしたわけではなく、どうすれば働けるかを真剣に考えたんです。それなのに、まるで“わがままを言っている”かのような扱いを受けて……正直、ショックでした。」
――その一言で、気持ちが大きく変わったのでしょうか?
里美さん「はい。初めて“私は歓迎されていないんだ”って、はっきり感じてしまったんです。
もし、まずは試してみようとか1ヶ月だけやってみて様子を見ようという返答があれば、私も諦めなかったと思います。そのような寄り添いもなかったので、私が歓迎されていなかったんだと思います。」
――会社としての姿勢に、何を感じましたか?
里美さん「在宅勤務制度はありますが、それを使えるかは空気と上司のさじ加減次第”。
社員の働き方が制度で定まっているのではなく、上司が決める会社では、何かあったときに安心して働き続けることは難しいと思いました。そして何より、“ここでは自分の声は届かない”と感じたことが、私の中で決定的でした。」
――異動などの選択肢は検討されましたか?
里美さん「もちろんです。もしこの部署で難しいなら、柔軟な運用が可能な別の部署で働くというのも一つの選択肢だと思っていました。実際に、“異動でもいい”という意思も伝えましたが、会社から異動という選択肢は一切提示されなかったんです。
子どもを育てていると、できれば安定した環境で働き続けたいものです。でも、対話の余地がないと確信したとき、ようやく“辞めよう”と決めました。」
――次の転職先は決まっているんですか?
里美さん「はい。同じように営業職の仕事なんですが、基本的にリモートワークです。打ち合わせなど必要に応じて出社することはあるんですが、それは全く問題ありません。実際に子育てしながら働いている人も沢山いるようなので、よかったです。
子育てしながら働きたい人は、在宅勤務制度があれば安心と思うかもしれませんが、本当に使えるのかどうかを確認することをおすすめしたいです。
里美さんの退職が示すのは、「制度があること」と「使えること」はまったく別物だという現実です。
制度自体は整っていても、実際に使えるかどうかは上司や部署の判断に委ねられており、申請する側にとっては“使ってもいいか”ではなく“使って嫌がられないか”が問題になっていました。人事としては、制度が現場で機能しているか、運用に偏りがないかを可視化し、誰もが安心して使える土壌づくりを進める必要があります。
また、制度を使おうとした社員が「特別扱い」と見なされるような空気を放置してしまうと、その会社で長く働く未来を描けなくなります。どれほど立派な制度でも、文化として根づいていなければ、制度は壁になってしまいます。社員の声が通らなかったのではなく、“届かなかった”ことへの失望こそが退職の引き金になります。
制度を整えるだけでなく、誰もが使えるものにすること。さまざまな制度を整備している会社は、現場と乖離が起きていないか、ぜひ確認してみてください。
新着記事
NEW
-
退職者のホンネが知りたい
-
退職面談「いっと」とは
-